
最近、「好きなチョコレートがまた値上がりした」「内容量が減った」と感じていませんか?その背景には、原料カカオの供給不足による価格高騰があります。
世界規模で広がるカカオの供給不足。主要産地・西アフリカの課題に加え、私たちが活動するインドネシアのスラウェシ島では、カカオの害虫が猛威を奮っています。ひどいケースでは農家が手塩にかけたカカオを9割も食い荒らしてしまうことも。
そこで、dari Kは、生産の現場からこの課題に取り組むプロジェクトを立ち上げました。
そのプロジェクトは、今年4月、経済産業省「グローバルサウス未来志向型共創等事業」に採択されました。事業テーマは「インドネシア・スラウェシ島におけるカカオ⾖の⽣産性向上とサプライチェーン強靭化実証事業」。カカオの病害や老木化の対策を行うことで、カカオの生産性を高め、供給の安定化を目指します。
→ 詳細プレスリリース
今回のブログでは、生産企画部・木澤の視点から、このプロジェクトを始めた背景や、カカオ農家の方々と共にどのような課題に取り組んできたのかご紹介します。
長期化するカカオの価格高騰
第1回の記事で取り上げたように、業界関係者の方はもちろん、チョコレートを購入してくださっている皆さまも、すでにカカオ価格の高騰のニュースはご存じかもしれません。昨年よりカカオの先物相場は急騰を続け、史上最高値を更新しました。

西アフリカでの病害虫や気候変動の影響が原因とされ、供給不安は世界規模に広がっています。
日本でも、チョコレート商品が一斉に値上げされたことで、
以前と比べればカカオの影響を身近に感じることも多くなったのではないでしょうか。
一般的に、原料の高騰の結果、起きることは、
- チョコレートそのものが嗜好品のため、消費者は買うのを控えます。
- チョコレート・メーカーは価格を据え置くために、カカオの使用量を減らしたり、新しいレシピに切り替えざるを得ず、市場全体のカカオ消費量も減少します。
実際の報道でも、ずっと伸び続けてきたチョコレートの生産量が25年4-6月期、アジアを中心に10%以上減少したと報じられました。
チョコレートの需要が減退しつつある一方、カカオの供給不足への懸念はそれ以上に強く、カカオの先物相場は今なお高い水準を保っています。
供給源の多様化とインドネシアの課題
チョコレート・メーカーとして通常、このような不安定な供給状況や、それに伴うリスクの解消に向け、対策を講じる必要があります。特に日本では、カカオの多くを「ガーナ」一ヶ国に依存してきたリスクを考慮し、「ガーナ」以外の国からも同時調達する事が1つの解決策になりえます。
その意味で、私たちが現在拠点を置くインドネシアのスラウェシ島は、アジア最大級のカカオ産地であり、供給上、最も重要な候補地の1つであると考えられます。しかし、スラウェシ島の現場でも、かつてないレベルで難しい問題に直面しています。
その1つが「カカオ・ポッド・ボーラー(Cacao Pod Borer。略してCPBと呼ばれています。)」という、害虫による被害です。この害虫は小さな蛾の仲間で、カカオポッド内部の果肉を摂食し、カカオの発育に必要な水分や養分の輸送を妨げます。その結果として発育不良なカカオ豆が生まれてきます。

発育不良のカカオ豆では、チョコレートに必要な発酵が十分にできず、品質低下を招くほか、豆同士が硬く固まって、それが農家による取り出し作業の大変な負担になったり、カカオの粒が小さくなったりと、全体の収量減少に深刻な影響を与え、もちろんカカオ農家の経済的損失に直結します。2年前から調査を続けてきた私の経験では、収穫したカカオの半分以上(50%以上)が食い荒らされてしまう、という事は全く珍しくありません。
最もひどいケースでは、収穫したカカオの9割以上が害虫被害に遭ってしまうことも。せっかく農家の方々が育てきたカカオをまったく買取できなかったとき、この害虫の猛威に圧倒されました。

そもそもカカオは、外側の殻を割って中身を確認するまで、栽培期間中の約3-4か月間、被害状況がなかなか、わかりません。(このようにカカオ豆は厚い殻で覆われています)

そのため、害虫による被害は、農家が数か月にわたる栽培や手入れを行った後になってから、カカオの収穫のときにはじめて、しかも、少しずつ明らかになっていきます。
この害虫の問題が、収穫後の現金収入を見込んでいた農家、そして、その家族にどれほど影響を持つ問題なのか、皆様にもご理解頂けるのではないかと思います。
発想転換:「供給懸念」から「供給をしっかり行うには何をすべきか」

こちらの写真は、害虫被害にあった大量のカカオ豆の中から、出荷可能な豆を一粒一粒、選別している様子です。こうした害虫問題の放置は、生産者の現金収入の減少だけでなく、大変に負荷のかかる作業をカカオ農家に強いることになります。
西アフリカで供給不安が生じる前から、私たちは深刻化するインドネシアの害虫問題に取り組む必要性を感じてきました。
当時、みんなで検討した結果、
効果的に害虫被害を抑制できる「独自の防除剤」を開発することにしました。
このブログでおなじみのヘルウィンさんやイチャルさん、そして農家の方々とチームを組み、既存の防除剤を用いながら、彼らのアイディアやニーズをもとに初期配合を設定し、それから複数の実験に取り組んできました。
これまで2年近く一緒に実験に取り組んだ農園では、防除効果がしっかり発揮されており、今のところCPB被害率が少なくとも30%未満にまで改善。もちろん、これは発酵にも最適で良質なカカオ豆の確保にも繋がっています。
ただ、やはり万能薬ではなく、
防除剤を噴霧する作業は、農家にとって作業負担になるなど、課題は存在します。

このように、まだ途上ではあるものの、カカオ農家の方々とは顔を合わすたびに
「つぎ、いつ防除剤の試験する!?」
「昨日、試験中のカカオ豆をちょっとだけ収穫してみたけど、今回もちゃんと効いてる!」
と、いつも明るく語りかけてくれます。
↑
いや試験区のカカオ豆はとったらアカンていっつもゆうてるやん!(私の心の声)

たしかに、私自身も、同僚仲間と現地で実を割った瞬間、中にぎっしりと詰まった健全なカカオを見るたびに、ほっと、心が落ちつき、安心した気持ちになれます。
数年前、害虫被害がはじめて深刻化したとき、大切なお客様からオーダー頂いたカカオ豆を果たして本当に調達できるかとても難しい局面に陥りました。
そのときの辛い思いは、インドネシアの方々と一緒に経験してきたので、
害虫のコントロールに成功し、1粒1粒きれいなカカオ豆を見るたびに「良かった。これでお客様にちゃんとお届けできる。」と、不安がなくなる瞬間が、余計に嬉しく感じるようになりました。
このような防除剤の効果を試す過程で、農家のみんなに農業指導をしてくれているイチャルからこんな話がありました。
イチャル「この防除剤の実験が良いのは、農家のみんなをただの対象として扱わないところだね。」
私(木澤)「そうだね、農家の方と一緒に考えながらやれてる感じ。農家のみんなはスプレー作業があるから、私が一番何もしてないね。」
イチャル「そうそう。木澤は何もしていない〜(冗談)」
私(木澤)「そういうイチャルもずっとタバコしか吸ってないじゃん。」
最後はいつもの笑い話になってしまいましたが、イチャルも、この実験ではただ単に依頼をするのではなく、農家のみんなの主体性があることを評価してくれているんだと思います。

私もそのときは特に何も考えずに話していましたが、確かに、チョコレートをお客様に提供するうえで、欠かせない役割を農家の方にも分担してもらい、カカオの供給自体を共同で安定させるという意識的な取組は改めて重要だと感じるようになりました。
なにより、最も長くお取引する企業様から頂戴するお声の1つに、カカオ農家の方々にも直接役立つ意義ある成長をずっとご期待頂いてきました。
この新しい課題についてもインドネシアの方々と私たちの発想を軸に、今後の最も重要なミッションの1つに位置づけなければいけないと感じてきました。
そのあと、カカオの価格高騰がはじまったとき、私たちもチョコレートを作る側として原料高騰に備えた目先の対応を急いできました。しかし同時に、なぜ供給が不安定になるかという根本的な問題にもこれから向き合わざるをえないと、さらに感じるようになりました。
当然、限られた私たちの活動だけでカカオの供給危機を止められる訳ではありません。
私たちがカバーしている調達エリアだけでも害虫被害に負けず生産量が安定する農園を、少しずつでも増やしていきたいと考えています。
とても困難な目標で、言うは易し行うは難きなのですが、少しでも前進させ、加速させるためにスタートしたのが冒頭でご紹介した「インドネシア・スラウェシ島におけるカカオ⾖の⽣産性向上とサプライチェーン強靭化実証事業」です。

チームで乗り越える「取引関係」の壁
最近はヘルウィンさん、イチャルさん、そして農園を実験のために一時提供してくれている農家の方々とは収穫して綺麗なカカオを見るたびに
「Sukses(スクセス)!」
※インドネシア語で「これも成功!」という意
と、言葉に出して喜びを分かち合います。
本来、みんな取引関係者で、価格交渉などでは、利害が異なる(時には対立してしまう関係)立場ですが、それにもかかわらず、今この場では、同じカカオの供給を担う者として、「どうすればカカオの収穫量を安定させられるか」という共通の目標に向かって、上述したような実践経験を今も毎日、積み重ねています。
このように、スラウェシ固有の課題に取り組む過程で、価格高騰問題が更なるきっかけとなり、最近はどうすれば今後も供給し続けられるかについて、みんなと一緒に考えることが本当に増えました。
また、お互いの関係性や今後のあるべき姿について考え直す、代えがたい機会になっています。その意味で、価格高騰問題は重要の教訓として積極的に捉えています。

最後になりますが、dari Kのチョコレートには、良質なカカオ豆と、カカオの適切な発酵が重要です。
これまで多くの方々の協力と時間を頂き、何度も研究を重ねてきた発酵技術をこれからも最大限に活かすためには、害虫被害をしっかり抑制して、良質なカカオ豆を確保することが、今まで以上に重要な任務になっています。
害虫と私たちは普段あまり関係のないように思えますが、本稿でご紹介した地道な取組みの先に、やがてはより多くのお客様に納得頂き、喜んでいただけることを信じて、更なる努力を重ねてまいります。
以上、拙い文章で恐縮ですが、このブログを通して、dari Kがスラウェシ現地でどのようなことに悩み、どのようにカカオを供給しているか、少しでも現地の状況が皆様に伝わると嬉しく思います。
これまでのカカオ豆価格高騰シリーズはこちら
【第1回】「カカオ産地から見えること」 元駐在員足立こころ
https://www.dari-k.com/blog_post/soaringcocoaprices1/
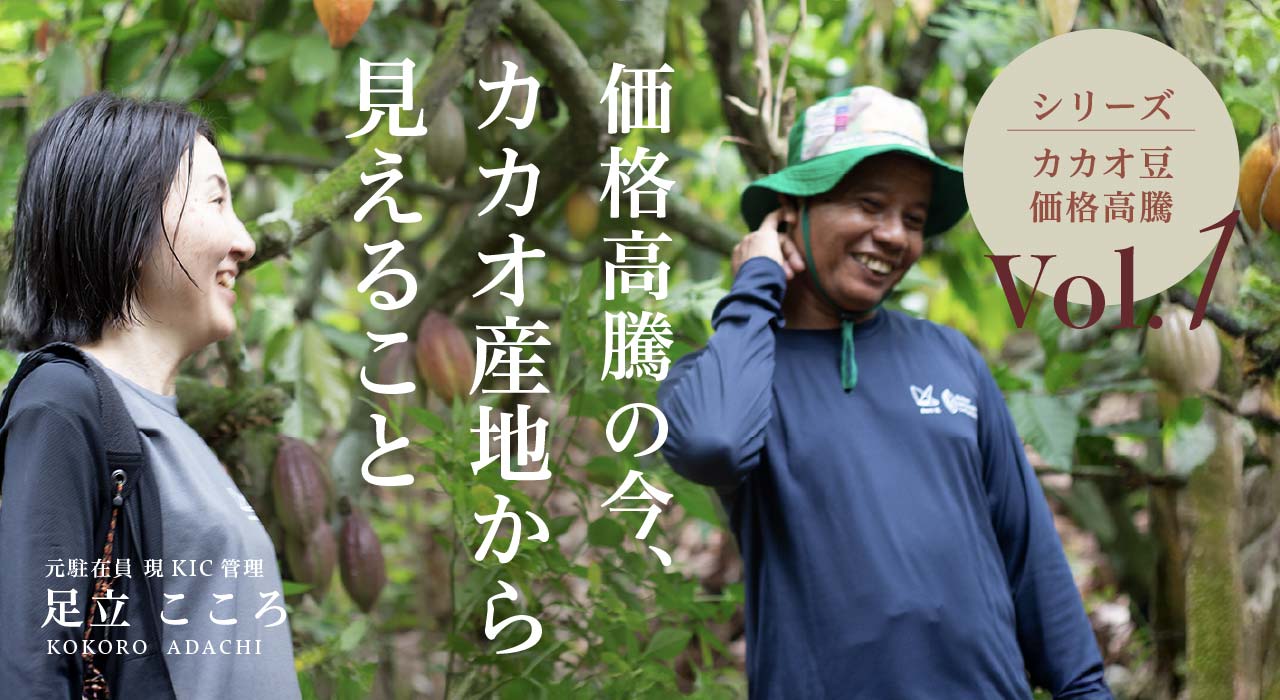
【第2回】カカオ高騰で「良い豆が評価される文化」は終わる?
dari Kが「カカオだからこそ」を追求する理由。商品開発担当の視点から
https://www.dari-k.com/blog_post/soaringcocoaprices2/

